
代表:品川真一
外壁塗装の業者選びで失敗しないために、複数の業者から見積りを取られることをおすすめします。ただし、ただやみくもに複数社から見積もりを取れば良いというわけではありませんので、ポイントを押さえておきましょう。
このページでは、複数の業者から見積りを取るときのポイントを解説しています。
外壁塗装にも存在する一括見積サイト。一括見積サイトに対する私の考えはこちらで書いています。
https://gaiheki.bosui.net/gyousya/mitsumori-site/
目 次
業者選びや見積りを取る前にご自身の要望を考えておく

お客様はどんな塗装業者をお探しでしょうか?一番安い業者ですか?あるいは、品質や保証・サービスが良い会社でしょうか?それとも上場企業でしょうか?
上場企業で品質もサービスも良く、しかも安い!そんな業者がいたら間違いなくその業者に頼みますよね。でも、残念ながら塗料という*半製品を取り扱う塗装業界ではそんな業者は存在しません。
*半製品とは・・・品質が安定しているのは塗料だけで、誰が、どんな道具で、何グラム、何回、どんな気象条件で塗るかによって工事品質が変わることから、塗装工事は半製品と言われています
そこで、お客様層とか業者層という考え方があります。お客様層とは、私たち業者側から見たお客様の特徴です。
例えば、
A:とにかく安ければよい
B:適正な価格で工事の品質・アフターフォローなどのサービスを重視する
c:高くてもハウスメーカーに頼んだほうが安心
など、何を重要視されるお客様なのか?ということです。これと同じように業者層もあります。
D:ただ安いだけの業者
E:適正な価格で工事の品質が高く、アフターフォローもしっかりしている業者
F:工事金額は高いけど会社規模が大きい業者
などです。
例えば、お客様がAのタイプで「とにかく一番安い業者に頼みたい」とお考えなのであれば、安さを売りにしている複数の会社から相見積もりを取って競争させるべきで、EやFの会社から見積もりを取っても意味がありません。
あるいは、Eの「適正な価格で工事の品質が高く、アフターフォローもしっかりしている業者」をお探しなのに、Dの「ただ安いだけの業者」を選んでしまうと失敗します。
このように外壁塗装の業者選びで失敗しないためには、お客様層と業者層が合うことが重要です。
まずは、自分にはどんな要望があるかを考えられて、どんな業者が自分に一番合っているかを決めましょう。
訪問販売が来ても即決しない
 塗装をするきっかけが「訪問販売業者が営業に来たから。」というお客様は少なくありません。塗装業者を選ぶうえで一番大切なことは、訪問販売が来ても即決しないことです。
塗装をするきっかけが「訪問販売業者が営業に来たから。」というお客様は少なくありません。塗装業者を選ぶうえで一番大切なことは、訪問販売が来ても即決しないことです。
国民生活センターが発表しているデータを見ると、訪問販売によるトラブル相談が毎年5~6千件もあります。それくらいトラブルが多いのが訪問販売の業者です。
詳しくは、「訪問販売員に外壁塗装を勧められている場合」で説明しています。
複数社から見積りを取り比べることが重要
訪問販売ではなくても、どのような業者で見積りを取ったとしても即決しないことをオススメします。なぜなら、1社のみの見積りだと、価格が高いのか?安いのか?判断できないからです。
もし、複数社の見積りを取り
・A社:100万円
・B社:110万円
・C社:200万円
このような見積もりだった場合は、少なくともC社は高いのかな?と判断できます。
また、業者が建物を見たときに
・A社:劣化はしているが、直ぐに塗装する必要まではない
・B社:劣化はしているが、塗膜が生きているので1~2年は大丈夫
・C社:今すぐ塗装しないと建物内部が腐り高額になる
このようなことを言われたときに、C社の言っていることが怪しいと判断することができます。
塗装業者選びで失敗しないためには、1社だけの見積りで焦って契約するのではなく、2~3社から見積もりを取り、落ち着いて契約することです。
塗装業者の見積金額に差がある理由
複数社から見積もりを取ると、金額に差が出ることがほとんどです。塗装業者の見積金額に差がある理由は、塗装工事は電化製品や車などとは違い半製品だからです。
安定した製品は塗料だけであり、塗装が完了して初めて製品になるので、製造過程が異なれば自ずと金額に差が出ることになるのです。また、工事を行う業者の業態によっても金額は変わります。
金額に差が出る理由は、次のようなことが挙げられます。
工程の違い
業者によって工程の違いがあるため、人件費や材料費なども変わってきます。
例えば
・A社:2回塗り工程
・B社:3回塗り工程
・C社:4回塗り工程
このような3社があったとします。C社はA社の2倍工程を必要としますから、その分コストは上がります。
「外壁を塗装する」とひとことで言っても施工内容が違うことは良くあります。そのため、値段が安いだけで契約するのは危険です。
中間マージンと粗利率の違い
中間マージンと粗利率は、会社によって違うため見積金額に差が出るのは当然です。
例えば、外壁塗装をハウスメーカーに依頼した場合、塗装専門店だと120万円の工事がハウスメーカーだと同じ内容で180万円ほどになります。
健全な経営をしていくためには30~35%の粗利益が必要ですが、ハウスメーカーの粗利益率は優に50%を超えているのです。
さらに、ハウスメーカーが発注する大手塗料メーカーの粗利益率も40~50%と高い比率です。これではお客様は無駄な中間マージンを上納するだけです。
業者の言うことが各社バラバラな理由
「複数社に見積りを取ったのですが、各社言うことがバラバラで困っています。ある業者がオススメしてきた塗料を、他の業者には良くないと言われました。こうなると一体何を信用すればよいのか…」
はい、よくあることですね。
例えば、
A社は「クリアー塗装で長持ちさせられますよ」と言い
B社は「クリアーは早く傷むから色付きの塗装をした方がいいです」と言われたとか。
あるいは、
B社は「シーリングは傷んでいるところだけ補修すれば大丈夫です」といい
C社は「シーリングはすべて撤去して打ち替える必要があります」と言われるなど、真逆のことを言われることもあります。
なぜ、このように各社が言うことがバラバラになるのか?これにはいくつかの理由が考えられます。
業者の勉強不足(無資格)で誤った診断をしている
塗装業界には、国家資格にはじまり民間のマイスターなどの資格があります。しかし、実は塗装業は塗装の資格を取得しなくても営業できるのです。
他社と違うことを言われた場合は、どちらかの業者が勉強不足(無資格)で誤った診断をしているかもしれません。資格を持っている業者なら、専門的で正しい知識を持っているので同じ提案になるはずですよね。
業者の売りたい塗料を提案している
お客様の家にあった塗料ではなく、業者の売りたい塗料を提案している業者は、自社開発の塗料を勧めて利益を出そうとしている場合があります。
その理由は、材料屋から仕入れた塗料よりも、自社で開発した塗料のほうが利益率が高いからです。
そのため、悪質な業者の場合は、他社が提案している塗料を「良くない塗料だ!」と言っていることもあります。
自社の職人が嫌がる塗料を否定する
営業マンは、自社の職人が嫌がる塗料は否定して、他社とは違う塗料を提案することがあります。
「あの塗料は塗りにくい」「あの塗料は養生が面倒くさい」「あの塗料は塗り回数が多いからやりたくない」という職人が塗装業界には多いのです。このように自社の職人がわがままな職人だったら、営業マンは職人がやりたがらない塗料をわざわざ勧めたりしませんよね。
例えば、ガイナは塗りにくい塗料なので嫌がる職人が多いです。また、クリアー塗料は養生が大変なので、やりたくないという職人が多いです。
自分たちが塗りやすい塗料、利益が出る塗料をお客様に提案しているのであれば、これはお客様目線ではなく自分本位の提案と言えます。
これを見抜くには施工実績を調べればわかります。もし、施工事例を見て同じほとんど塗料しか使っていない場合は注意が必要です。
世の中には色々な建物があり、それぞれ外壁の種類も構造も異なりますから、本来であればそれに合った塗料を選択する必要です。
「自社職人より下請け職人は良くない」は間違い
・自社職人は高品質な施工をする
・下請け職人はダメ
このように考えているお客様は多いです。下請けに丸投げするような会社だと確かにこの通りです。
しかし、自社職人でも下請け職人でも、会社本体がしっかりと管理していれば、問題はありません。ゼネコンの現場で働いている職人は、すべて下請け業者の職人です。それでもしっかりと仕事をします。
大切なのは、現場監督を置いて、誰が塗装しても一定以上の品質を確保できるようにする仕組みを作ることです。
職人は80点の仕事しかできないとしても、現場監督の指示通りに手直しをすれば95点の仕事にすることも可能です。だから職人と監督の両方が必要なのです。
仕事は職人で決まるのではなく、監督を中心とするチームで決まるのです。だから自社職人であろうと下請け職人であろうと関係ありません。チームとしてどうであるかが重要なのです。
現場監督の必要性については、「塗装工事には現場監督が必要な理由」で説明しています。
業者の良し悪しを暴く質問例
 数社から見積り提案を受ける際に、業者や担当者の良し悪しを見抜く一番良い方法は質問を投げかけることです。
数社から見積り提案を受ける際に、業者や担当者の良し悪しを見抜く一番良い方法は質問を投げかけることです。
このページに書いてある質問を聞いてみてください。ポイントはその場で質問することです。メールだと返答までに調べられるので、その場で質問するのがベストです。
例えば、私がお見積りさせていただいたお客様でこんなエピソードがありました。あるサイディングボードに塗装ができるか、できないか、という悩みを抱えられていたお施主様が業者にこう質問されたのです。
『このサイディングには塗装できますか?』
質問された業者の担当者はそれぞれ違うことを言ったそうです。ある者は『調べてきます』、またある者は『わかりません』と。その中で『塗れますよ』と即答したのが弊社だけだったそうです。
別に特別なことをしたわけではありません。塗料メーカーと元サイディングメーカー勤務の方から、新製品の下塗り材が発売されたことを聞いて知っていたから即答できたのです。
その道のプロなら、常に最新の情報を知っていなければなりません。外壁塗装工事を商品をしているプロの業者として当たり前のことをしただけです。常に最新の塗料やあるいは塗料のトラブル事例なども情報収集して勉強し、正しい情報や工法を提供できるようでないとプロとは言えないと思います。
一般の消費者からの質問に答えられないプロに100万円以上もする外壁塗装工事を頼もうという気になりますか?私なら絶対に頼みません。
以下は、業者の良し悪しを暴く質問例です。
Q.工期は何日かかりますか?
外壁塗装工事は誰がやっても最低12日はかかります。
工程順に並べてみますと以下のような流れになります。
01日目:足場組
02日目:高圧洗浄
03日目:乾燥養生
04日目:各所養生
05日目:下塗り
06日目:中塗り
07日目:上塗り
08日目:付帯部塗装
09日目:付帯部塗装
10日目:養生撤去
11日目:各所手直し
12日目:足場解体
このような流れです。ただし、これは12日間連続で雨が降らなかった場合(湿度が85%未満だった場合)、1日1工程ずつ進めた場合です。実際には雨が降ることもありますから、その分工期が延びることになります。
さらに、この工程には検査が入ってません。11日目の後に社内検査と手直し、そのあとに引渡し検査が入るので、実際には最低でも14日間は必要になります。
そこで、「工期は何日かかりますか?」と質問してみることをお勧めします。例えば「一週間くらいです」と返答があった場合、明らかに工数が足りませんから、手抜き工事をされる可能性が高いので要注意です。
大同防水では、外壁塗装だけなら通常で14日工期をいただき、屋根+外壁塗装の場合は20日間の工期をいただいております。
Q.ここは塗ってもらえるのですか?
見積り書の内訳書を見ると、外壁塗装○○㎡とか、樋塗装○○m、破風塗装○○mなどと項目が書いてあると思います。
お客様はどの項目がどこの部位なのかわかりますか?見積書上は専門用語ばかりでわかりにくいはずです。そこで業者と実際に家の周りを見て回って、「ここは塗ってもらえるのですか?」と質問してみてください。
「そこは塗りますよ」「そこも塗ります」と返答があったとします。最初から塗る予定なのであれば、どうして見積書に記載しないのでしょうか?約束事はすべて記載する必要があります。
もしかすると、お客様に指摘されなければ塗らないつもりだった可能性もあります。こういう業者は怪しいので要注意です。
例えば、ベランダの笠木や手摺りは紫外線の影響で色褪せていたり、手摺の部分に傷が入っていることが多いので塗装したい部位ではないかと思います。
その他では、土台水切りや換気口、ガス管、門灯や外灯、ポストなど、付帯部で塗装が必要な部位はたくさんあるので、部位毎に塗って貰えるのかどうかを事前に確認しましょう。
Q.基礎がひび割れてるのが気になるのですが?
「基礎がひび割れてるのが気になるのですが、このままで大丈夫でしょうか?」この質問は、その業者が建物知識に詳しいかどうかを見抜くための投げかけです。
外壁塗装は一般的に基礎より上の部分です。基礎の補修や塗装は含まれていません。でも住宅の寿命を考える点で最も重要なのは、建物を支える基礎です。
一般的に、大手ハウスメーカー様の住宅の基礎は耐用年数40年で設計されており、地元の工務店様らの基礎は耐用年数30年で設計されていると言われています。
基礎部分はコンクリートで造られており、表面にモルタルが1㎝程度塗って仕上げてあります。このモルタルがひび割れていると気になりますよね。特に割れやすいのが換気口回りです。
コンクリート基礎は、ひび割れても強度はほとんど低下しません。ですから、「基礎のひび割れを補修しないと危険です」などと言ってくる業者は間違っています。
お客様が劣化状態の中で最も不安になるのがひび割れですから、そこを突いてきて煽り営業を強いられることがよくあるので注意が必要です。
Q.どうしてこのプランを提案されるのですか?
業者が提案してきた塗装プランの理由を知りたいと思いませんか?
どうしてその塗料なのか、他のメーカーではダメなのか、大切なことはその塗料が長持ちするのかどうかということより、お客様のお家に相性が良い塗料なのかどうかです。そして、お客様は説明を受ける必要があるはずです。
もしかすると、そのメーカーの塗料しか取り扱っていないのかもしれません。あるいはシリコン塗料しか使ったことがない業者は、フッ素塗料を勧めてこないでしょう。これは、お客様の都合ではなく業者の都合ですよね。
ひとつのメーカーの塗料しか扱わない業者は、おのずと情報量が乏しくなります。例えば屋根と壁にシリコン塗料を塗った場合と、屋根はフッ素塗料を塗って壁にシリコン塗料を塗った場合との違いを、その業者は知る由がありません。
サイディングボードに相性が良い塗料と、モルタルやコンクリートに相性が良い塗料は違います。なんでもかんでも同じメーカーの同じ塗料を提案してくる業者も少なくありません。
ポイントは、その塗料がお客様のお家に相性が良い塗料なのかどうかです。
「どうしてこのプランを提案されるのですか?」この質問を投げかければ、その塗料を提案してきた理由がわかります。答えられない業者には注意です。お客様のお宅に最適な塗料を、しっかりした理由で説明できる業者こそ優良な業者です。
Q.違うメーカーの塗料で施工された物件を見せてもらえませんか?
どの建物にも同じメーカーの塗料を提案する業者がいますが、ひとつのメーカーの塗料の実績しかない業者は不自然です。
例えば、お客様のお家にはテレビや冷蔵庫、洗濯機、オーブンレンジ、掃除機など家電製品があると思いますが、メーカーはすべて同じですか?おそらく、メーカーはバラバラではないかと思います。
それと同じように、サイディングボードに塗る塗料はメーカーA社の塗料、モルタル壁に塗る塗料はメーカーB社の塗料、屋根に塗る塗料はメーカーC社の塗料という具合に、メーカーはバラバラになるはずなのです。
すべての部位に使う塗料が同じメーカーの塗料という業者は、お客様の都合に合わせた提案をしているのではなく、業者の都合で提案していると考えられます。
なぜなら、一つのメーカーの塗料しか扱わない方が在庫管理もしやすいし、社員が覚える塗料の情報量が少なく済むからです。
しかし、そうは言っても本来なら一軒一軒違うお家に最適な塗料を提供するには、取り扱うメーカーはおのずと複数社になるはずです。
業者が提案してきていない他のメーカープランでの施工物件があるかどうかを聞けば、その業者が何を売りたくて何を売りたくないのか、あるいは何を売れないのかがわかります。
Q.長持ちさせるポイントを教えて下さい
「外壁や屋根を長持ちさせるポイントは高耐久グレードの塗料を選ぶこと。」という風に答える業者が多いと思います。確かに、ウレタンよりシリコン、シリコンよりフッ素塗料の方が長持ちします。
しかし、最も重要なのは下地処理工程です。どのグレードの塗料を使っても、下地処理工程を疎かにしてしまうと長持ちしません。
仕様はフッ素仕上げなのに1回しか塗らなかったり、素地調整を行わなかったりすれば本来の塗料の性能が発揮されず、結果として寿命は短くなります。
どんな塗料を塗るにしろ、しっかりと下地処理を行い、高耐久グレードの塗料をできるだけ多い回数で塗る、というのが長持ちさせるポイントです。劣化が早い屋根や南西面の外壁だけ塗り回数を増やすというのもよい策だと思います。
「長持ちさせるポイントを教えて下さい」この質問を投げかけることで、その業者が長持ちさせるポイントを知っているか、塗装工程で何が重要と考えているかがわかります。塗料グレードについてしか話さない業者には注意が必要です。
Q.あと何年持つでしょうか?
塗装を考えられているお客様のお家に伺って診断してみると、塗装できない状態であったり、塗装できない建材の場合もあります。
特にカラーベストやコロニアルと呼ばれる平板スレート屋根には、塗装できない・塗装しない方が良い屋根材もあるので、正確な診断能力が問われます。
もし塗装してはいけない屋根材を塗装してしまうと、数年後に剥がれてお客様が損をすることになります。塗装できない屋根は、張り替えるかカバー工法になりますが、どうしてもやらないといけないのかどうかです。
もし屋根をメンテナンスしなければあと何年持つでしょうか?と質問してみてください。今すぐやらなければならないのか、あるいはメンテナンスしなくてもあと5年くらいは持つのか、はたまた10年は大丈夫なのか、業者の見解を比較するのです。
メンテナンスしなければ見た目はどんどん悪化していきますが、このまま放置しても雨漏りしたり致命的な欠陥にならないのであれば、メンテナンスしないという選択もありですよね。

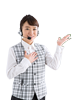 お気軽に
お気軽に




















 満足度96.8%!
満足度96.8%!






