
Q.サイディングの反りかえりは補修できますか?
お答えします。サイディングの反りは補修で改善できるものと多少は良くなるもの、改善できないものがあります。ここでは改善できるものについて説明します。
サイディングの反り、気になりますよね。どうみてもここから雨水が浸入してしまうことはあきらか。
でも大がかりな張替えは費用がかかるからやりたくない。できれば安く直せる方法はないかなぁ?とお考えの方も多いでしょう。そんな悩みも実はビス1本で解決します。
サイディングボードの反り(そり)の原因
サイディングボードが反りかえる要因として、サイディングの厚み・水分・熱・釘の抜けなどが挙げられます。
厚み:昔の12mm厚のサイディングによくみられる
サイディングボードを使う場合、現在は14mm以上の厚みのものを使用しなければいけないと定められています。ですが、それ以前は12mm厚が基本で、この頃のサイディングボードに反りかえり現象がよく見られておりました。
外壁塗装をする際、このまま塗装しても段差ができるので仕上がりが不細工になりますし、雨水が入りやすくなるので補修が必要になります。
水分:サイディングの側面から雨水を吸い込み乾燥収縮が起きる
そもそも窯業系サイディングボードは、セメントに木くずを混ぜたものなので性質はコンクリートではなく、木として考えなければなりません。
そのため、目地シーリングの劣化によって目地部分に雨水が浸入すると、サイディングボードの断面から吸水してしまい、湿潤⇔乾燥を繰り返すうちにサイディングの変形・反りかえりが起きてしまいます。
釘抜け・熱:温度変化でによるサイディングの収縮で釘が抜ける
サイディングボードが反りかえる原因で最も多いのは。釘の抜けです。
たとえば、下地の構造用合板(コンパネ)の節部分に釘を打ってしまったり、ジョイント部分に打ってしまったりすると釘が効かず、さらにサイディングボードは熱の影響を受けやすいので、温度変化によって釘が浮いてしまうことがあります。
とはいってもサイディングを張る工程では合板の弱い部分がどこにあるかは見えず、偶然の不可抗力ですので職人さんを責めることはできません。
サイディングの反りかえり部分の補修方法
長手方向にU字型に湾曲してしまったサイディングは張替えになりますが、軽微な反りかえり程度であればビス留めで収まります。
1.現状
 これが現状です。
これが現状です。
このままではシーリングを打ちかえても簡単に切れてしまうので、補修が必要です。
まずは目地シーリングを撤去し、サイディングにかかっている力を解放してやります。
次に、反りかえり部分がどこから始まっているか、手で叩きながら把握します。
2.ビス留め
 反りかえりが始まっている部分の釘に遊びがあるようであればビス留めで直りますので、釘の遊びを確認するのがポイントです。
反りかえりが始まっている部分の釘に遊びがあるようであればビス留めで直りますので、釘の遊びを確認するのがポイントです。
ここで釘に遊びがない場合はサイディングボード自体が変形してしまっているので、ビス留めでは直りません。
また、サイディングが直張り工法か通気工法かによってビスの長さを変える必要があります。
通気工法の場合は、胴縁(どうぶち)の木の上にビスを打ち込むようにします。木胴縁(もくどうぶち)の位置は釘の位置でわかりますので、釘が打ってあるライン上に留めれば問題はありません。
3.完成
 1か所のサイディングの反りかえり補修に、ビス(木ねじ)2~3本使いました。
1か所のサイディングの反りかえり補修に、ビス(木ねじ)2~3本使いました。
あとはビス頭を外壁の色と似た色でタッチアップすれば完了です。このように正しい手順で補修するとまっすぐに戻ります。
ビスをあまり端っこに打つとサイディングボードが割れてしまうことがあるので、注意が必要です。確実に割れを塞ぐ方法として、ビス径よりも小さい径の下穴を開けるのが有効的です。
サイディングの反りかえり補修の注意点
-

-
目地部分が青く見えるのは、絶縁用のセロハンです。シーリング材が直接、目地底にくっつかないようにするために張られているもので、建築用語ではボンドブレーカーといいます。
青色の右側にシルバーの部分が見えていますが、これはハットジョイナーという目地に入れる金物のつばの部分です。
本来は青色の部分だけ見えるはずですが、この画像ではシルバーの部分まで見えています。つまりサイディングボードが縮んでしまったわけです。
このままシーリング材を充填しても問題はありませんが、サイディングボードというのはこのように熱収縮を繰り返す外壁材なので、シーリング材も適したものを使わなければ簡単に切れてしまいます。
※サイディングの反り返りは、必ずしもビスで補修できるというものではありません。サイディングの反りに遊びがなければ、無理やりビス留めしようとするとサイディングが破壊されてしまうので、くれぐれもご注意ください。いかなるトラブルが発生しても当社では一切責任を負えません。
サイディングの反りかえり部分を補修する時のポイント
・サイディングの厚みを調べる
・釘が浮いているかどうか(遊び)を確認する
・反りかえりが始まっている部分からビス留めしていく
・ビス頭をタッチアップする
・端っこにビスを打たない(打つと割れることがある)
・下穴を開けておくと割れにくい
・直張り工法か通気工法かでビスの長さを決める
・通気工法の場合は胴縁の上にビスを打つ

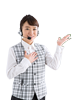 お気軽に
お気軽に

















 満足度96.8%!
満足度96.8%!






