
これが膨れ現象
-

-
外壁の塗装が膨れている建物がありますが、どうして風船のように膨れてしまうのでしょうか?
例えば、左の画像のように塗装が膨れてしまい、ダラ~ンとダレている場合は、塗装を切開すると水が出てきます。つまり雨水が外壁と塗膜の間に回ってしまっているのです。
ではどこから雨水が回ってしまったのでしょうか?
-

-
正解はこちらです。
赤線部分に防水の端末押さえ金物が取り付けられており、この部分から雨水が浸入して塗膜の裏側に回ってしまったのです。
この場合、防水の施工に落ち度があったと考えられます。塗装業者としても、こうなることくらいは知っておかなければなりません。
膨れる塗装と膨れない塗装がある
全ての塗料が膨れるものではありません。
膨れてしまう塗料は弾性塗料、つまり柔らかくゴムのように伸びる塗料が膨れるのです。
塗料は弾力性が増すほど空気を通す力が減ります。つまり柔らかい塗料は空気(湿気)を通さないということです。ですから、ひとたび水分や湿気が塗膜の裏側に存在すると、風船のように膨れてしまうのです。
弾性塗料の膨れを防ぐ為には「雨仕舞い」が重要
-

-
お祭りのときにヨーヨー釣りと言って、水風船を引っ掛けて釣りますよね?あの水風船は風船の中に空気と水を入れてありますが、まさに塗装が膨れているのはこの水風船と同じ状態なのです。
風船はゴムですから、空気を入れると伸びて膨らみますよね。水を入れてもこぼれません。
では、どこから水分が塗膜内部に浸入したのか?ということですが、まずひび割れがない限り、塗装面(塗膜)の一般部分から水分が浸入することほとんどありません。
塗装の弱点は端部です。端部に不備があると、塗装した翌日からでも浸入してしまいます。
弾性の塗料の場合は、外壁に密着しているというよりは「外壁にふわっと乗っている」と思ってください。要するに完全に密着していないのです。
塗料は弾力性が増すほど密着力が減ります。この二点の理由から、柔らかい塗料を塗ると、端部から雨水が回りやすくなると言えます。
ですから、塗装は塗装、防水は防水、ではなくて、塗装と防水をひっくるめた雨仕舞いを考えることが重要なわけです。
膨れた塗装の補修方法と対策
膨れた塗装は切開・撤去し、中の水を抜いて乾かします。皮を剥いた状態になりますから、段差ができますので、左官補修して段差をなくします。
次に元の塗装パターンに合わせて模様をつけ直し、その後塗装をします。
しかしこれではまた同じことを繰り返してしまうので、防水の端末部を改修します。端末押さえ金物から雨水が浸入しないようにすればOKです。

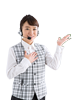 お気軽に
お気軽に

















 満足度96.8%!
満足度96.8%!






